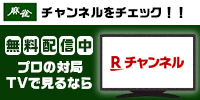中級/第106回:中級講座『山読み~プロセス~』 山田 浩之
2015年10月21日
今回から中級講座を担当させていただく山田浩之です。
ご存じない方もいらっしゃると思いますので簡単に自己紹介をさせていただきます。
17期生。六段。プロ入り16年目。A2リーグ所属。
自分の雀風は、打点重視の面前バランス型。読みには多少自信があるので終盤勝負が得意です。
自分が麻雀を打っているときに考えていることをみなさんにお伝えし、雀力向上の一端を担うことができればと思っております。
よろしくお願いいたします。
連盟Aルール
南3局 東家 5巡目 29,400点持ち(トップと4,700点差の2着目)












 ツモ
ツモ ドラ
ドラ
配牌はぱっとしなかったものの3巡目にドラの が重なり、ツモ
が重なり、ツモ でピンズがリャンカンになったところです。
でピンズがリャンカンになったところです。
みなさんは何を切りますか?
おそらくは、 を切る方が圧倒的に多いのではないかと思います。
を切る方が圧倒的に多いのではないかと思います。
でも自分は、実戦で を切りました。ではなぜ
を切りました。ではなぜ ではなく
ではなく を切ったのか。
を切ったのか。
まず、ドラがトイツで234や456の三色も狙えるチャンス手ではあります。
しかし、5巡目で1メンツも無い3シャンテンと、アガリたい手ではあるのですがスピードに欠けます。
でももしここで が重なったら仕掛けがきくようになりスピードもアップします。
が重なったら仕掛けがきくようになりスピードもアップします。
それを逃さないためにも、まだここでは を手放したくありませんでした。
を手放したくありませんでした。
しかも現在6ブロックあるターツオーバーの状態で、もし今 を切ったところで、次巡
を切ったところで、次巡













ツモ や
や 、
、 、
、 で、やはり
で、やはり のトイツ落としを選択することになると思ったのも理由の1つです。
のトイツ落としを選択することになると思ったのも理由の1つです。
であれば、今 を切り
を切り の重なりを期待したほうがアガリ率は高くなるというのが自分の考えです。
の重なりを期待したほうがアガリ率は高くなるというのが自分の考えです。
もちろん をひいてアガリを逃すこともあるので、一概に
をひいてアガリを逃すこともあるので、一概に 切りが正解というわけではありません。
切りが正解というわけではありません。
中級講座を読んでくださっているみなさんでしたらきっと、過去に何切る問題をやったことがあると思います。
何切る問題を解くことは、牌効率や手順を覚えるためにとても有効です。
そしてそれを実戦で活用するためには、答を覚えるだけではだめなのです。
麻雀は全く同じ局面には遭遇しないと言われています。
似たような場面で、その知識を応用して打牌選択を行うためには、その打牌のメリット、ディメリットをしっかり把握することが必要になるのです。
少し話がそれましが実戦に戻しましょう。
 、
、 と引き込んで以下の牌姿となりました。
と引き込んで以下の牌姿となりました。














そして他家の捨て牌が
南家 






西家 






北家 






こうで、際立った特徴はありませんが、字牌の整理が早く普通に(七対子やホンイツ、チャンタではなく)手を進めているといったとこでしょう。
安全牌として字牌を持たずに打ち出しているということは、3者ともアガリに向かっているのは間違いありません。
ヤミテンが入っている可能性もありますが、1シャンテンぐらいではないでしょうか。
ということは、 が重なったものの、まだスピードでは追いついていない。
が重なったものの、まだスピードでは追いついていない。
そして場にピンズが高く、マンズの下が安く が山にいると思ったため、ここでは打
が山にいると思ったため、ここでは打 としました。
としました。
 と
と は情報が無く、山に残っているのか全くわからなかったのですが、後手を踏んで場に高いピンズのリャンカンが残ったままでは戦いにくいのではと思いました。
は情報が無く、山に残っているのか全くわからなかったのですが、後手を踏んで場に高いピンズのリャンカンが残ったままでは戦いにくいのではと思いました。
そして、 引きでの両面変化や、456の三色もまだみたいということもあり、この巡目からピンズを全部払うのは危険だと思いつつも、打点もあるためリスクを負う価値があると判断したのです。
引きでの両面変化や、456の三色もまだみたいということもあり、この巡目からピンズを全部払うのは危険だと思いつつも、打点もあるためリスクを負う価値があると判断したのです。
実戦は、 、
、 と引きテンパイはしたのですが、結局アガることはできませんでした。
と引きテンパイはしたのですが、結局アガることはできませんでした。
アガリという結果がでなければ成功とは言えませんが、そこに辿り着くまでのプロセスも大事だと思います。
よく勉強会で若手に伝えていることがあります。
「麻雀が強くなりたかったら大事な局面でしっかり考えて、自分なりの答を出す」
私はこれがが大切だと思います。教わるだけでは身にならないのです。
そしてその結果、失敗に終わっても、結果だけにとらわれず、違う選択肢はなかったのかもう一度考えてみる。
その繰り返しで精度をあげていくのです。
次回は、序盤から中盤にかけての手組みについて書きたいと思います。
また、こんなことが聞きたい、教えてほしいなどありましたら是非お問い合わせ ください。
それではまた来月(^_^)/~。
カテゴリ:中級